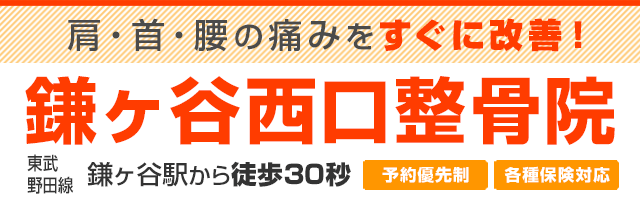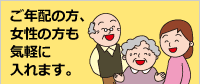巻き肩

こんなお悩みはありませんか?

肩こりや首こりが続き、痛みがなかなか引かないことがある
長時間のデスクワークやスマートフォン使用により姿勢が崩れている
肩や背中の筋肉が硬くなり、柔軟性が落ちている
呼吸が浅くなり、深く息を吸うのが難しく感じる
頭痛やめまいが起こることがある
肩甲骨の可動性が低下し、腕が上がりにくくなるほか、体型が崩れて見えることもある
巻き肩について知っておくべきこと

巻き肩は、肩甲骨が前方に出て、肩が内側に丸まった姿勢を指します。この姿勢は、長時間のデスクワークやスマートフォンの使用、筋力の不均衡などが原因で起こりやすくなります。巻き肩は、首や肩の痛み、頭痛、腕のしびれなどを引き起こす可能性があります。
巻き肩をそのままにしておくと、慢性的な痛みや姿勢の悪化につながるおそれがあるため、早めに対策を行うことが大切です。日常生活の中で姿勢に注意し、定期的に運動やストレッチを取り入れることが推奨されます。特に、胸の筋肉を伸ばすストレッチや、背中の筋肉を強化することが重要です。
また、長時間デスクワークを行う場合には、こまめに姿勢をチェックし、背筋を伸ばすよう意識することが大切です。
症状の現れ方は?

巻き肩の一般的な症状として、まず肩が前方に巻き込まれた状態が続くと、首や肩の筋肉に過度な負担がかかり、痛みやこりが生じることがあります。特に、デスクワークやスマートフォンの使用が多い方に見られる傾向があります。
また、肩が前に出ることで胸の筋肉が短縮し、反対に背中の筋肉が弱くなることがあります。これにより姿勢が乱れ、猫背になったり、肩甲骨の動きが制限されることもあります。
さらに、巻き肩は呼吸にも影響を及ぼす可能性があります。胸部が圧迫されることで深い呼吸がしづらくなり、浅い呼吸が続く状態となります。その結果、疲れやすくなったり、集中力の低下を感じることもあります。
巻き肩は外見にも影響を与えることがあり、それがきっかけで自信を失うこともあります。このような姿勢の乱れは、長期的に関節や筋肉の機能に負担をかけるおそれがあるため、早めに対応することが大切です。
その他の原因は?

1. 長時間のデスクワーク
デスクワークを長時間行うことで、前かがみの姿勢が続き、肩が前方に巻き込まれることがあります。特にパソコン作業では、画面に集中するあまり、姿勢が乱れやすくなります。
2. スマートフォンの使用
スマートフォンを見続けることで、首や肩に負担がかかり、巻き肩を引き起こす可能性があります。特に下を向いた姿勢が長時間続くと、肩が前方に巻き込まれやすくなります。
3. 運動不足
運動不足により筋力が低下し、特に背中の筋肉が弱くなることで、肩が前方に引っ張られやすくなります。このような状態は、巻き肩を引き起こしやすくします。
4. 筋力のアンバランス
胸の筋肉が強く、背中の筋肉が弱い状態では、肩が前に出やすくなります。特に胸の筋肉が緊張していると、肩を後ろに引く力が不足し、巻き肩の傾向が強まります。
5. 姿勢の悪い習慣
日常生活における姿勢の悪さや、不良姿勢での長時間作業は、巻き肩の原因となることがあります。特に座っているときや立っているときの姿勢に注意が必要です。
巻き肩を放置するとどうなる?

1. 慢性的な痛み
巻き肩の姿勢は首や肩、背中に過度な負担をかけるため、慢性的な痛みやこりを引き起こすことがあります。これにより、日常生活やお仕事のパフォーマンスが低下する可能性があります。
2. 姿勢の悪化
巻き肩を放置すると、猫背や背中の丸みが進行し、姿勢がさらに乱れる傾向があります。その結果、身体全体のバランスが崩れ、他の関節や筋肉にも負担がかかる場合があります。
3. 呼吸の制限
巻き肩による胸部の圧迫により、深い呼吸がしづらくなります。浅い呼吸が続くと、酸素の供給が不十分になり、疲労感や集中力の低下につながることがあります。
4. 自律神経の乱れ
巻き肩によって筋肉が緊張し続けると、自律神経のバランスが崩れることがあります。その影響で、ストレスを感じやすくなったり、睡眠の質が低下する可能性があります。
5. 心理的な影響
巻き肩は見た目にも影響を及ぼすため、自信の低下や自己評価の低下につながることがあります。こうした心理的要因が、メンタル面にも悪影響を及ぼすことがあります。
当院の施術方法について

当院で行っている施術方法は、主に4つあります。
1.猫背矯正
この施術は猫背に対してアプローチを行うもので、ストレッチ系のメニューとなります。巻肩に関連する筋肉に対して主にストレッチを行うことで、巻肩の軽減が期待できます。
2.肩甲骨はがし
肩甲骨の動きを引き出すことにより、肩にかかっている負担を分散させ、関節へのアプローチを通じて巻肩の軽減が期待できます。
3.筋膜ストレッチ
この施術は上半身・下半身どちらにも対応しておりますが、巻肩に対しては上半身のストレッチを行います。肩周りの筋肉を中心にストレッチを行うことで、巻肩に関与している筋肉へアプローチしていきます。
4.矯正
この施術では巻肩に対して骨格的なアプローチを行い、根本からの軽減が期待できます。
軽減していく上でのポイント

姿勢の意識
日常生活やお仕事中に正しい姿勢を意識することが大切です。肩を後ろに引き、胸を開いた姿勢を保つように心がけましょう。特に座って作業をされる方は、定期的に姿勢を確認し、背筋を伸ばすように意識することが重要です。
ストレッチ
胸の筋肉をストレッチすることで、短縮している筋肉をゆるめることが期待できます。壁に手をついて胸を開くストレッチや、ヨガのポーズなどを取り入れることが効果が期待できる方法です。
筋力トレーニング
背中や肩まわりの筋肉を強化することで、巻肩の軽減が期待できます。特に肩甲骨を引き寄せる動作を意識したエクササイズが有効です。たとえば、ダンベルローイングやチューブを使用したトレーニングが挙げられます。
定期的な運動
全身の筋力バランスを保つためには、継続的な運動が効果的です。有酸素運動と筋力トレーニングを組み合わせることで、姿勢の軽減が期待できます。
デバイスの使い方を見直す
スマートフォンやパソコンを使用する際は、画面の高さを目線に合わせて、前かがみの姿勢にならないよう工夫しましょう。また、長時間の使用を避けて、こまめに休憩を取ることも大切です。
生活習慣の見直し
睡眠や食事、ストレス管理も姿勢に影響を与える要素です。十分な睡眠をとり、バランスの取れた食事を心がけることで、身体全体の健康維持につながります。
監修

鎌ヶ谷西口接骨院 院長
資格:柔道整復師、鍼師、灸師
出身地:茨城県かすみがうら市
趣味・特技:スノーボード、ダーツ